Comment|コメント・メッセージ
片岡翔 [映画監督・脚本家]
松井良彦 [映画監督]
私が興味を抱いたのは、鶴岡監督が日々の生活でおこる物事に、何を感じ、どう考え、どのように捉えて、過ごしているのだろうかということです。
というのも、この映画には監督の好奇心による視点と感受性が、巧みなタッチと相まって、観る者を愉快にさせてくれるセンスに結びついていると感じたからです。
だから、十数人の登場人物の気持ちが、しっかりと受けとめることができ、そして、そこに生まれた若者ならではの、繊細で、愛くるしく、時に未熟な、そんな心の動きが煌(きら)めいていると思ったのです。
吉田浩太 [映画監督『好きでもないくせに』]
うつろう人間が交差し、捻じれ、重層化していく複雑な関係性を、丹念にシンプルに紡ぎ出していく――物語の終盤、知らぬ間にうっすらと目を潤ませている自分に気づきました。
映画全体を纏う端正なニュアンスが、確かな演出に裏打ちされた独自な色気として立ち上り、俳優を魅力的に映し出しています。監督が俳優の良さを信じて作っている映画なんだなと思います。自分の職業柄、女性監督でこれほど女性を綺麗に撮られる方がいることに大変驚きましたし、嫉妬しました。
リアルとフィクションの垣根をさらっと越えていく、独自かつ実験的な音楽の遣い方は必見です。
古厩智之 [映画監督]
若者たちの群像。
元彼の葬儀前。喪服のファスナーを上げ、真珠のネックレスを付け、じっ…と静止する彼女。
ヌードデッサンに行くことを喜ぶ彼。上目使いに見て「行かなくていいよ」と笑う彼女。彼女は彼が好きなのだ。
2人が向かい合って話し合うと不穏が満ち、並んで歩くと安らぎと幸せが昂ぶる。それはとっても映画的だ。
ていねいに、愛おしげに造形される若者たちは、慈愛と優しさに溢れていて、良き神様が作った標本箱のように見える。
夕暮れの陽射しも、しとしと降る雨も、若者たちを集めるのと同じように愛おしくコレクションされていて、その手つきは「収集」でなく、ただ「そっと隣にいる」ようだ。
自分の彼女に横恋慕する友人。それに怒ってた男が、自分のほうこそ二人の関係に後から入ってきた存在だった、と聞かされて「俺、最悪だー!」と叫ぶ。
想いを寄せる喫茶店マスターがうたた寝してる間に、好きな歌をそっと歌ってみる女。
彼ら彼女らが、自分の生命力に突き動かされて手脚や羽をバタバタと動かす瞬間に、標本箱から幸せが溢れる。
生きてるぞ! それこそが奇跡だぞ! と。
いいなあ! 鶴岡さんの詩心に満ちた人間賛歌でした。
高柳恋 [作詞家]
僕達は、なにか言おうとするたびに口ごもる。
この映画に、凶悪な犯罪者は登場しない。派手なカーチェイスも大爆発も。人々は小さな声で喋り、靴音を大袈裟に響かせないで歩く。身体じゅうが震えるような高揚とは無縁だ。しかし、取るに足らない様々なものが、実はとても大切で愛おしいことを、鶴岡慧子監督は知っているのだろうと思う。
カメラマンが死ぬ。最後に撮った1本のフィルムを残して。しかし、死因は明かされないままだ。フィルムになにが写っていたのかも。それでいいのだと思う。ささやかな悲しみを、些細な嫉妬を、漣のような恋を、謎を斑に、マーブル状にかき混ぜる。決して完全に撹拌するのではなく。答えはない。ただうつろうだけだ。
劇中の最後のひと言が、ブレヒトの異化効果なのだろう。どこにでも起きそうな、現実と同化してしまいそうな物語の最後には、相応しいひと言だったのではないだろうか。
僕達は、なにか言おうとするたびに口ごもる。口ごもりながらこの街の片隅で胸を張って生きる。それを出来ることが幸せというものなのかもしれない。
最後に、黒木渚さんの言葉遣いには驚かされました。
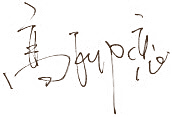
三宅章太郎 [CMプランナー/劇作家]
今を生きる人間たちの、したたかで鮮やかな脈動を感じさせる物語。標本箱に留められた昆虫たちをずっとずっと見つめているような作品です。
柏木白光 [書家]
千利休の「一期一会」の言葉は刹那の大切さを、幾たびおなじ主客と交会するも、今日の会に再びかえらざるを思えば実にわれ一世一度の会なりと説いています。
人はそれぞれの人生をひとりで歩いているように見えるけれども、その人生は何層にも複雑に重なり合い干渉し合っている。人がかかわれば個々の想いも発生し、気の持ちようで良くも悪くも転がるということがよくあり、言い換えれば心のあり様で辛さが和らぐことだってあります。花が好きで美しいと思う人には花は匂いたち、空を見あげる人には優しく緑の風が吹くのです。
全ては自分の心一つなのです。
一筋の光に人々が心を寄せ日々を暮せばとても嬉しい事だと映画を観て感じました。
水谷修 [夜回り先生]
次から次と現れるヒーローでもなく悲劇の主人公でもないごく普通の若者たち。カメラがひたすら追い続ける彼らの日常。その中であらわになる人の不器用さ、弱さ。交差する出会いの中で産まれてくるものは・・・。考えさせられました。
渡辺真起子 [俳優]
うつろっているのは、世界なのか、わたしなのか。
それぞれの「うつろい」それ自体がぐるぐると渦を巻き始め、巡り会い、大きな瞬きを描いていたように思う。
フレームの中の、その人が、振り向いた、覗きこんだ、睨みつけた、微笑んだ、クッと。
その存在が、私の心にチクっと刻まれました。
木下ほうか [俳優]
もちろん山ほど映画を観てきたし、出てもきた。たまにこんなチャーミングな作品と出会い、手作り感に好感が持てる。次作にも期待したい。
安川有果 [映画監督]
誰かの死をきっかけにして物語が始まる(登場人物が動き始める)映画は多いですが、この映画は、誰かの死をきっかけに物語をはじめようとする人物が存在しないところが新しく、そこに鶴岡監督の品を感じました。
なぜなら、死んだカメラマンの元彼女も、元同級生も、死体を発見したカップルも、彼の人生のある地点ですれ違っただけの、持続する関係、未来への約束のない存在だったから。そのことが、彼の死と関係がないとはいえないのかもしれない。
そんなうっすらとした悲しみが映画全体を支配し、ただ日常を大切に生きるということのかけがえのなさが、鮮やかに浮かび上がってくる。そのことは、彼が撮った写真に証拠として収められている。
カメラマンの松島が最後に同級生と会ったときの泣き笑いの表情は、ずっと私の心に残り続けると思います。
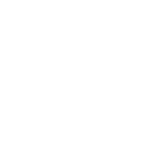

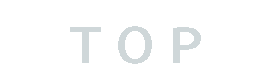



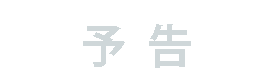
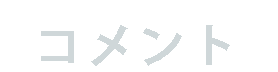

とても儚くて、でも美しい女性たちの標本箱。
彼女たちがゆるやかに悩みつつ、懸命に生きているさまは、
映画という物語の中ではなく、この世界、この現実そのものを映し出しているようでした。